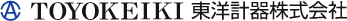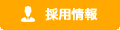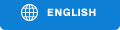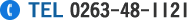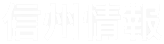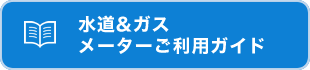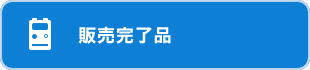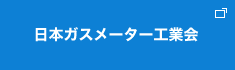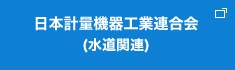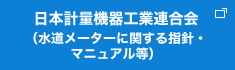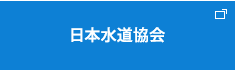2015年8月15日 松本「水巡り」
湧水の町・松本
周囲を山に囲まれた松本。その山々に長い時間をかけて磨かれた水が女鳥羽川と薄川として流れ、松本の地は複合扇状地となっています。豊富な地下水は市街地の至る所で今も湧水として湧き出し、「まつもと城下町湧水群」として環境省が選定する「平成の名水百選」に認定されています。
どの湧水も味が異なりますが、真夏でも冷たい水が人々の喉を潤してきました。井戸も意匠がこらされ一つとして同じものはなく、見る人を楽しませてくれます。
湧水群を代表する2つの井戸

天保14年(1843年)に刊行された「善光寺道名所図会」では「当国第一の名水」と称賛されています。歴代城主は不浄を禁ずる制札を立てこの清水を保護したといいます。
町の酒造業者がこぞって使ったという「源智の井戸」、現在ではここの湧水を使ったコーヒーや信州蕎麦を堪能できるお店も近くにあります。

四角いブロックのような形が特徴的です。
中町通り

左の「蔵の井戸」は、酒造場の母屋・土蔵・離れの3棟を移築し公共施設として再利用している「中町・蔵シック館」の広場にある、手押しポンプ式の井戸です。
何回かレバーを上下すると、勢いよく地下水が飛び出します。


「吾唯足知」と書かれた趣ある井戸。

「草庵」というお店の店先で発見。

藤森病院併設の井戸「亀の泉」初代院長・藤森亀太郎氏が名前の由来。

「善光寺街道辻井戸」
縄手通り~松本城近辺

商店街隣にある願いごと結びの神社「四柱神社」の向かいに、水量の多い湧水があります。後ろ側は滝になっており、松本城を守るように走る川「女鳥羽川」に勢いよく流れ込みます。
囲むように茂る木々の木陰が涼しく、水と風の音が爽やかなスポットです。

昔この場所にあった井戸を、読売新聞松本支局建て替えに伴い再建しました。

「お城の見える井戸」から見た松本城

「大名町大手門井戸」松本城の表門があった場所。

「大名小路の井戸」街歩きに疲れたら隣のベンチで一休み。

「東門の井戸」昔この場所には最大の馬出しがありました。

「辰巳の御庭井戸」江戸時代の松本城主・辰巳の御殿があった場所。

「西堀公園井戸」ここの水が一番美味しく感じました。

「外堀小路」城下町松本にはこのような小路が多くあり、探検のようで心が躍ります。
松本市美術館周辺


「日の出の井戸」モダンなスタイルの井戸。

「日の出の泉薬祖水」他の井戸が枯渇しても決して枯れなかったと伝えられている、薬祖神社内にある井戸。
紹介したもの以外にも、松本にはまだまだ多くの湧水・井戸があります。街歩きの際に見つけたら、飲み比べてみるのも良いでしょう。また、マップを持って井戸巡りをするのもおすすめです。松本を訪れた際には、ぜひ水の綺麗さを堪能していただければと思います。
※飲用不可の湧水・井戸もありますので、注意書きをお読みの上ご利用ください。
番外編
松本市の南に位置する上伊那郡 辰野町。県内では「辰野町と言えば蛍」というイメージが定着するほど、蛍の名所として有名です。
町が「日本一のほたるの名所」と謳う松尾峡・ほたる童謡公園では6月中旬から下旬にかけて「ほたる祭り」が開催されます。
期間中、辰野駅周辺は土日を中心に屋台が並び、パレードなどのイベントが行われ、賑やかなお祭りの雰囲気に包まれます。

賑わうお祭り

懐かしの屋台
屋台を抜けるとお祭りの賑わいが段々と遠ざかっていき、静かな田んぼ道を提灯の明かりを頼りに10分ほど歩きます。蛙の鳴き声、お線香の匂い。日本の夏を肌で感じ、日々の喧騒を忘れられます。
ほたる童謡公園内は蛍の光を見やすいように、電灯などの明かりは一切ありません。
殆ど真っ暗な状態で柵から川を覗くと…

長時間露光で撮影した蛍。

今では珍しくなった蛍ですが、ほたる童謡公園では多い時で6000匹近くの蛍の乱舞を鑑賞できます。淡い光が宙を舞う幻想的な景色に時間を忘れて見入ってしまいました。
水の綺麗な川に生息する蛍。信州の水の綺麗さ、豊かさを実感します。